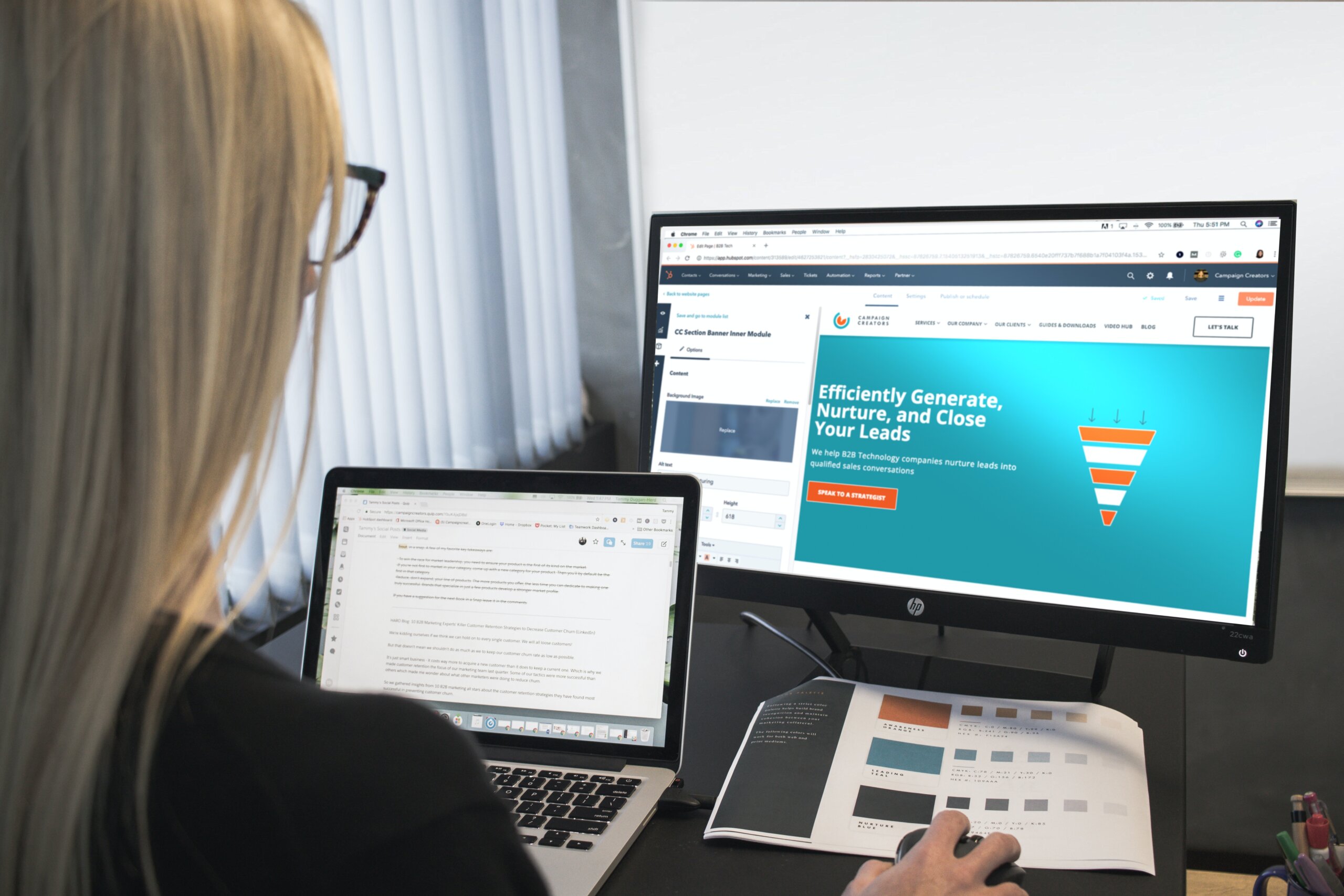コロナ禍によって既存の仕組みから大きな転換を迫られた昨今、教育も例外ではなくなりました。オンライン授業を実施するため、学習支援システムを導入した学校も多いのではないでしょうか。
ですが、コロナ禍も落ち着いた今となっては、コロナ前に戻った学校が多くあります。
オンライン学習支援システムはオンラインでの授業だけに対応しているわけではありません。適切に運用することで、多くのメリットを得られます。
今回はオンライン学習支援システムを導入するメリットと手順について解説します。授業の負担を減らし、より子ども達と向き合うための時間が欲しい方は必見です。
オンライン学習支援システムとは授業を効率化できるツール
オンライン学習支援システムとは、先生の授業や生徒の学習を支援するためのツールです。様々な機能を使って総合的に授業を支援してくれます。結果、授業の効率化ができる点が大きな特徴です。
システムは大きく分けて以下の3つに分けられ、それぞれ対象が異なります。
- 校務支援システム:教育委員会や校長など
- 授業支援システム:校長や管理職など
- 授業支援ツール:管理職や教科担当など
何ができるかはシステムによって個別に違うため、欲しい機能を選ぶことが大切です。
代表的な機能
オンライン学習支援システムは提供している企業によって、何ができるかは異なります。ただし、ある程度の共通化はしています。例えば、システムによって得られる以下の効果は同じです。
- 効率化:先生や生徒の負担を軽くする
- 付加価値:システムによって人にはできな効果を得る
これらのバランスを取りながら、何のオンライン学習支援システムを使うかを決めていかなくてはいけません。
難しいと感じる方は、以下に代表的な機能を記載していますので参考にしてください。
| 生徒・教師管理 | 名簿管理・編集 グループ管理 |
| 教材管理 | 教材登録・配信 動画作成・配信 宿題配信・採点・回収 履修状況の把握と管理 |
| 授業準備サポート | 入退室管理 出欠管理 授業計画の作成 スケジュール管理 |
| 授業サポート | オンライン授業 メッセージ配信 チャット機能 デジタルノート ファイルの配布・提出・採点 カメラ機能 Webテスト アンケート |
| 授業記録管理 | 指導報告書管理面談記録成績管理評価 |
オンライン学習支援システムを導入するメリット
オンライン学習支援システムを導入するにあたって、知っておきたいのがメリットです。果たして導入することでどのようなメリットがあるのでしょうか。
効率化・付加価値の両方の面から深掘りしていくと、以下のメリットが得られることがわかります。
- コア業務に集中できる
- 学習効率が上がる
- データの活用が簡単にできる
- オンラインにも対応している
- 登校できない生徒も参加できる
- 学校外と連携できる
コア業務に集中できる
オンライン学習支援システムは先生の業務をサポートしてくれるツールです。そのため、現在抱えている業務量を軽減でき、コア業務に集中できます。
文部科学省が行った「教務支援システム 導入・運用の手引き」によると、導入した学校の7割以上が業務時間の短縮に成功しています。
日々の雑務をシステムに投げた結果、コア業務に集中できる環境が整ったためです。結果的に働き方改革にも成功しています。
学習効率が上がる
オンライン学習支援システムは何も先生だけにメリットがあるわけではありません。学生にとってもメリットがあります。例えば、システム上でデジタルの教科書を使えば、教科書を持ち歩く負担を軽減できます。
他にも、課題の回答の共有やディスカッション時の資料配布など、様々です。体育祭や文化祭にも活用できるでしょう。
このように、より効率的に勉強や人間関係を学習できる環境の構築が可能です。
データの活用が簡単にできる
オンライン学習支援システムは、データの活用が簡単にできる点もメリットと言えます。データの蓄積・分析はシステムが最も得意とするものだからです。
例えば、成績や学習のデータを蓄積してグラフや表で可視化すれば、より効果的な授業を行えます。年間を通して蓄積していくことで、その年の傾向も見えてきます。これまで通例化・属人化していた取り組みを、データを元に客観的に検討・実施できるのです。
オンライン学習支援システムを導入することで、データの活用が簡単になるでしょう。
オンラインにも対応している
オンライン学習支援システムは、その名の通りオンラインに対応しています。コロナ禍において、最も活躍したツールの1つと言っても過言ではありません。
例えば、動画配信機能のあるシステムであれば、授業のオンライン配信ができます。システムによってはアンケート機能やディスカッション機能まで搭載されているため、実際に教室で授業を受けているような感覚で参加できます。
このように、オンラインに対応していると、実際の教室とは違った取り組みが可能です。
登校できない生徒も参加できる
オンライン授業は、自宅にいながら授業を受けられます。そのため、登校できない生徒も参加できるメリットがあります。例えば、以下の生徒です。
- 怪我や体調で登校できない生徒
- 何らかの事情によって登校できない生徒
- 不登校の生徒
こうした生徒にも授業を受けてもらえます。実際の教室では対応が難しかった部分も、オンライン学習支援システムなら簡単にクリアできるのです。
学校外と連携できる
オンライン学習支援システムなら、学校外とも連絡できます。オンラインならではの強みですね。
先述した登校できない生徒はもちろん、外部の人に講演を依頼する際にも利用できます。授業を依頼する際に、選択肢が増えるのです。
更に学生同士の交流にも活かせます。姉妹校との国際交流もオンラインなら容易です。
このようにオンライン学習支援システムを導入すれば、学校外と簡単に連携できます。
オンライン学習支援システムを導入する手順
オンライン学習支援システムを導入する際に知っておきたいのが、導入手順です。多くの企業から様々なサービスが提供されているため、最適なシステムを選ばなければいけません。以下がオススメの導入手順です。
- 導入の目的を明確にする
- システムの仕様を決める
- 導入テストをする
- 全校で展開する
- 結果を検証する
Step1.導入の目的を明確にする
オンライン学習支援システムを導入するにあたって、必ず決めておきたいのが導入の目的です。導入した結果、どのような状態を目指すのかを明確にしておかなければいかせん。
目的が明確でないと、機能の選定で失敗する可能性が高くなります。現場からの賛同も得られにくいでしょう。
部署や立場の垣根を越えて、複数人から多角的な意見をヒアリングしてください。目指すべき目標が見えてきます。
Step2.システムの仕様を決める
導入の目的が決まったら、次はシステムの仕様を決めます。ヒアリングした内容を実現できるシステムを選びましょう。
選択した仕様によっては費用が大きく変わる可能性もあるため、予算と相談しながら慎重に選ぶ必要があります。場合によっては優先順位の低い機能を捨てる可能性も。
難しい判断になるため、システムの仕様は慎重に決めてください。
Step3.導入テストをする
システムの仕様が決まって使う準備が整ったら、次は導入テストを実施します。いきなり実施しては現場が混乱するためです。
まずは小さな範囲で導入し、初期不良や不具合がないかどうかをチェックします。この際、同時にマニュアルや運用ルールを作っておくと便利です。
本格展開した際に、スムーズに使用できる環境を構築できます。まずは導入テストで感触を見ましょう。
Step4.全校で展開する
導入テストが問題なく進んだのなら、いよいよ全校で展開します。テスト時に作成したマニュアルや運用ルールを最大限活かす機会が到来します。
ですが、オンライン学習支援システムの導入はこれで終わりではありません。次に続きます。
Step5.結果を検証する
オンライン学習支援システムは導入して終わりではありません。導入した結果、どのような効果があったのかを検証することが大切です。例えば以下のような。
- 設定した目標が達成されたのか
- 問題がどれだけ起こったか
このように、検証するべき項目は多々あります。オンライン学習支援システムも、通常業務と同様にPDCAがとても大切です。常にPDCAを回し続け、最大限活用していきましょう。
そのためにも結果の検証は非常に重要です。
オンライン学習支援システムは授業全般を支援してくれるツール
オンライン学習支援システムは、授業全般を支援してくれる頼もしいツールです。業務をシステムが肩代わりしてくれることによって、業務の効率化はもちろん、コア業務に集中できます。オンラインを通じて、登校できない生徒に授業を受けてもらうのも簡単です。
導入時は、まず何を目的にするのかを明確にしましょう。その上で仕様を決め、導入テストの後に全校稼働してください。もちろん、PDCAを回して常に改善していく姿勢を忘れてはいけません。
もしオンライン学習支援システムで悩んでいるなら、『Revot』がオススメです。生徒の様子の見える化はもちろん、取得したデータをもとにAIが業務を助けてくれます。これまで100社以上の企業に導入され、経済産業省の支援プログラムにも採択されています。ぜひ1度お気軽にご相談ください。